剪定をしている時に考えることは、、
「この枝を切っても良いのかなぁ」
「でも、残すと良くないのかなぁ」
「どこで切るかなんて考えたってわからないし、ジャマだから切っちゃお」
と、頭の中でいろいろ考えてしまうかもしれないです。
色々悩んで切っていると心も体も疲れてしまって、作業が捗らなかったりします。
今回は、枝を切る時・残す時に考えると剪定が楽になる方法を書いていきます。
剪定で残す枝と残さない枝の違い【切る枝は自由に選べます】
残す枝はその場所で役割があります。
単純に言うと、形を作るためです。
残さない枝はその逆で、切れば形も透け具合もきれいになるということになります。
残す枝と残さない枝の見分け方が分かるように、それぞれの特徴と残すか残さないかの考え方を分けて書いていきます。
残す枝の特徴

残す枝の特徴は次の通りで、、
・間延びしていない
・適度に新しい枝や芽がある
・他の枝に絡んでいない
これらは残します。
「間延び」とは?

間延びとは、太い主な枝の途中や先端から伸びている枝が、すごく長く先端にしか枝分かれがない状態です。
きれいな木の形は、枝分かれを繰り返しながら先端に近づくにつれ細くなって広がりを作っていくのが理想です。
間延びが増えると形が崩れやすくなります。
なので、なるべく間延びしている枝を切るようにして、細かい枝を残すようにしましょう。
適度に細かい枝や芽があればそこで切り戻すこともできるし、他の枝に絡んでいなければ剪定が楽になり形を整えやすくできます。
残す枝の決め方と考え方と切り方

決め方
残す枝の単純な決め方は、枝が細かいことです。
枝分かれをたくさん繰り返していればその分枝が細くなり、細かい見た目になると思います。
剪定は、ほとんどが枝分かれをしている箇所で切ることを繰り返す作業です。
なので、枝分かれがたくさんあれば、切る位置を自由に調整することができます。
考え方と切り方
例えば、今、目の前にある枝と上下左右の枝を観察してみたとします。
そうすると、大体同じような位置に枝分かれがあることが多いです。
同じような位置にある枝分かれを目安に剪定したとすると、枝分かれの通りの形に仕上がります。
切ったことによって葉の枚数が減り少し透けて風通しが良くなり、大きさは最初より小さくなるはずです。
文字で書くとこんな感じで、一言でいうと「枝分かれが切るところの目安」って感じです。
残さない枝の特徴と利用方法

・飛び抜けて長い
・枝分れがない
・他の枝に絡むように伸びている
この3種類の枝は、基本的には元から切ってしまって大丈夫です。
ですが、これらの枝を切ると枝が無くなってしまうような場所は、途中で切っておくこともできます。
途中で切っておくことで、新しい枝を作りなおして形を整えていくイメージです。
切る位置は、枝の元から5㎝くらいで切っておいて、次の年に新しい枝が出たら残したい枝を選んで剪定していきます。
毎年これを繰り返していくと、枝が増えて細かい枝を作れます。
長い枝の利用方法

残さない枝・不要枝・長い枝が出やすいのは、枝数が少なく栄養の分散が上手くいっていないと考えられます。
木が大きくなるにつれて根が広がっていくとその分栄養を多く吸い上げていくので、枝が伸びやすくなったり幹が太くなりやすくなったりします。
そのバランスを保つように不要枝を途中で切って、枝数を増やしてあげると強く伸びる枝が減ってくると思います。
このイメージを頭の片隅に入れておくと「今回は枝を増やす剪定をして様子をみてみようかな?」「こっちの枝は他の枝に絡んでいるから元から切った方が良いな」などを考えながら剪定ができると思います。
切る枝の自由な選び方「ここが大事です!」

枝を切る時は、基本を守りつつ自由で柔軟な考えが必要です。
基本的には、枝の向きが幹から見て外向きになるように剪定していきます。
この基本を忠実に守って手入れしたとすると、一枝一枝がぺったんこというか厚みが全くないようなイメージになってしまいます。
これを回避するための柔軟な考え方は、、
・上向きから外向き
・内向きから外向き
・下に垂れている枝を外向き
こんな感じで、外向きにはこだわるけどそこに至るまでの枝の向きは基本から外れても大丈夫という考え方です。
ちょっと強引な考え方と感じるかもしれませんが、すべての枝ではなく時にはこのような方法も必要ということです。
今現在必要ではない枝を途中で切っておいて次の年に新しい枝が出たら外向きにして、透かしながら形を整えていけば大丈夫です。
木を植えたばかりでまだ小さい場合でも、大きな木を小さくしたい場合でも剪定の基本はあまり変わりません。
3本の枝があったら真ん中を切って2本の枝を残すようにするのも基本なのですが、どの場合もこの方法を使います。
これを柔軟に考えると、枝が1本しか残せなかったとしても隣の枝をもう1本と見て2本の枝であるとみることもできます。
今手入れしている枝だけ見るのではなく、少し周りを見渡して「他の枝と併せて考えてみれば基本に合うようにできそうだな!」と考えられます。
今やっていることに真剣になりすぎず、自分の感覚を広げながら剪定してみると色々なことに気が向いて覚えられる幅も広がると思います。
まとめと剪定している人の考え
剪定をする人みんなが、どの枝をどのくらいにしようかを自然と考えていると思います。
一番最初に書いた「どのくらいで切ったら良いか分からない」「ジャマだから切っちゃおう」とか、人それぞれの感覚で作業をしています。
切る場所や切り方を知らなければ、一時的にでもサッパリすればそれでいいというのは自然なことです。
それが間違いということはないと思います。
ですが、ほんの少しでも知識として切り方の基本を覚えておけば、それだけでかなり違いが出るはずです。
その少しの違いがあれば毎年自分のためにもなるし、剪定を始めた頃とは木の様子も変わってきます。
最初は木を切ることに慣れるために形とか気にしないで大丈夫で、まずはやってみることが大切です。
木を切るのも片付けるのも結構大変なので、自分のペースで無理せずやってみてください。
楽しくできれば一番いいですが作業的に合う合わないがありますので、気楽にできる時にやっていきましょう。
剪定の基本に関しての記事も下に貼っておきますので、お時間のある時に読んでいただけたらと思います。
最後まで読んでくださりありがとうございました!
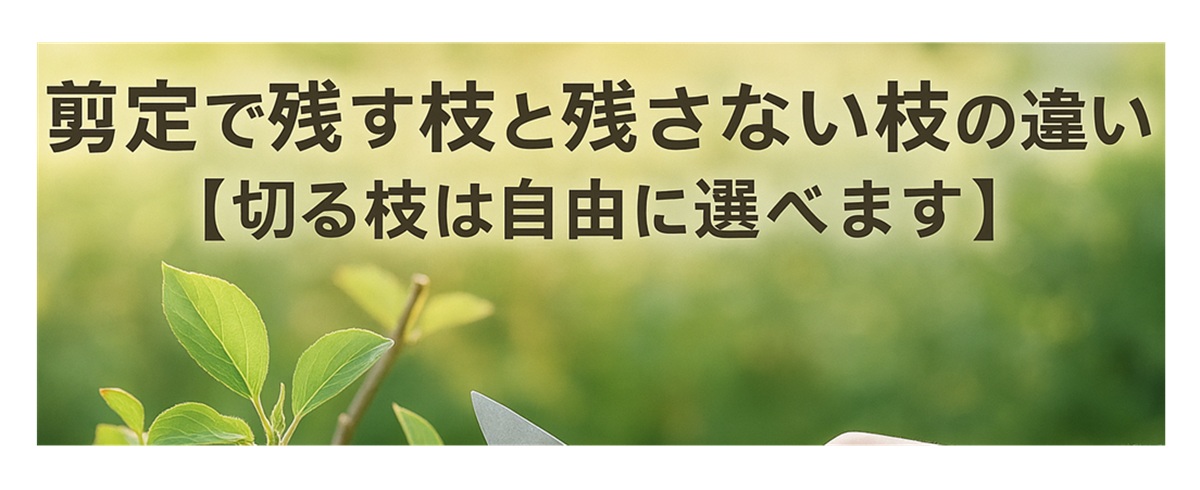





コメント